【プチ旅>京都】建仁寺霊源院(けんにんじ れいげんいん) 親切な若和尚、歴史の深い宝物と、最新のお庭。
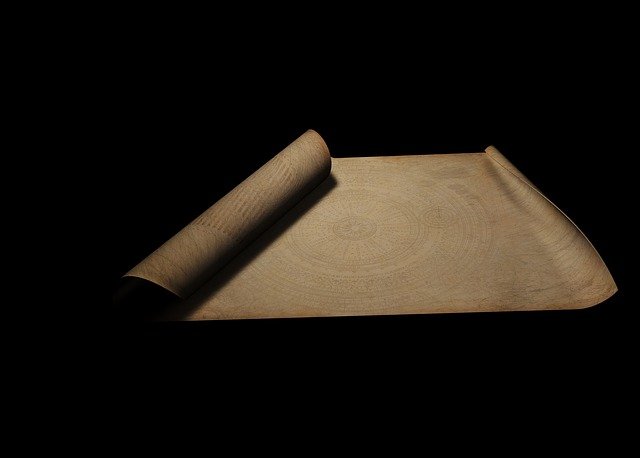
きれいなお庭とものすごい宝物が見られるお寺「建仁寺」のお話です。
- 歴史や文化に興味のある人
- 京都を観光する予定のある人
- 庭園や美術品が好きな人
1つでも当てはまっていればOKです!
開け放たれた扉から見えた、美しい景色
建仁寺霊源院の前を通りがかったところ、扉が開け放たれていて、奥のお庭がめちゃくちゃ鮮やかに見えました。テレビの4KのCMに出てきそうなまぶしさです。
入観料500円かかりましたが、入ってみることにしました。

建仁寺 門
きさくな和尚
受付の女性に入館料を払うと、「和尚がご説明しますのでお待ちください」、と言われ、ほどなく若めの和尚が近くへ来ました。
和尚に説明してもらったことなどないので戸惑いましたが、そんな動揺にはかまう様子もなく、すぐそばにあった掛軸の説明が始まりました。
宝物 織田信長の直筆の書状も
はじめの掛軸はこのお寺の創立に関わった方で、日本人で中国(当時の元)に渡ったが、晩年日本に帰ってくるよう懇願され帰ってきた龍山徳見(りゅうざんとくけん)。
龍山さんと離れたくなくて日本についてきた中国人の僧侶林浄因(りんじょういん)は、日本にまんじゅうを伝えたという功績も残しています。
まんじゅうは日本発祥ではないのですね。またいかにも日本らしい”抹茶”も、中国から伝わったものだそうです。
建仁寺霊源院は学問の禅寺として名門で、一休宗純(一休さん)や、今川義元(戦国七雄とされ、桶狭間の戦いで織田に敗れる)もこのお寺で学んだそうです。
次に極小の二畳の茶室(千利休が最もおもてなしに適する広さとした)に入れてもらいましたら、床の間の掛軸は、なんと織田信長の直筆の書状でした。専門家の先生に見てもらったところ本物だとわかったそうです。信長がノリにのっていた時代で、建仁寺への無茶な要求が書かれていたり、信長という名前のサインのクセなども教えてもらいました。カバーやガラスもなくそのまま掛けてあるので、こんな貴重なものを通りすがりの一般人が(ワンコインで)じかに見られていいのだろうかと戸惑いました。
美しいお庭
お庭は有名な庭師・中根金作氏の孫、中根行宏氏・直紀氏の作品だそうです。2020年に作った(リフォーム?した)新しいお庭で、造っている風景を動画で見せていただきました。早送りされていたので、長すぎず・端折りすぎずでちょうどわかりやすい映像でした。
インドから輸入した座布団型の石には、ぜひ座禅してみてくださいと言われたので、踏み外して白い砂利のみぞを壊さないように、ビビりながら踏み石をたどっていきました。
座布団石の上は、いちだんと静かで、音だけでなく、空気も静かになった感じがしました。

お庭は屋敷を囲むようにあり、正面は戦国時代に好まれた庭、右側は江戸時代に好まれた庭、と見比べることが出来ます。
戦国時代は、高さのある荒々しい岩々。音楽や映画などなかったので、このように見た目で闘志を燃やしていたのだろうということです。そのように想像したことがなかったので、とても納得できました。
逆に江戸時代は鶴と亀がテーマ、低く、平べったく、丸みのある岩が使われています。太平の世を望んでいることが反映されているそうです。
和尚の”中国人はゼロからイチを作るのが得意、日本人はイチをニ・三と増やすのが得意。”という話に納得しました。
お話を聞いてもヘエ、とかハア、とかまぬけな相槌しかできないにも関わらず、わかりやすい例えで笑いを交えながら説明してくれました。
和尚って頭いいんだな、たしかに昔話とかで知恵を授けるイメージだけど、実感したな。という日でした。
祇園界隈を散歩する方は、少し奥まっていて見つけにくいですが、ぜひ探してみてください。
まとめ
- 建仁寺霊源院は、学問の禅寺として今川義元や一休さんなど歴史上の有名人が学んだ場所である
- 織田信長直筆の書状や、再建された美しいお庭が見どころ
- 気さくな和尚が丁寧に説明をしてくれるので、予備知識がなくてもまったく問題なし
よろしければ試してみてください!
最後までお読みいただきありがとうございました。
↓↓京都の街中、四条河原町の観光をしたい方はこちら↓↓


