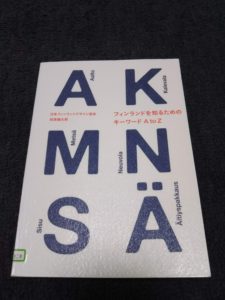【本>小説】春琴抄(しゅんきんしょう) 谷崎潤一郎

明治期の大阪が舞台の、盲目の女三味線師匠のお話です。
谷崎潤一郎。小説を読むのがあまり得意でない私にとって、国語の授業で「細雪」の作者だとかろうじて覚えたなという認識です。最近、阪神間地域について知りたくて「阪神間の文学」(武庫川女子大学文学部国文学科編集)という本を読んだところ谷崎潤一郎の人生(下記)をわかりやすく書いてあったので、小説も読んでみたくなりました。まずは代表作の細雪を読もうと思ったのですが、図書館には上中下の”中”しか空いていなかったので、有名作とあった、「春琴抄」を読んでみました。比較的短いので私のように初めて読む方にも良いと思います。
- 明治時代や大阪の歴史に興味がある人
- 関西弁や地方方言に興味がある人
- 盲目の主人公や音楽の世界で活躍するストーリーに興味がある人
- 昔の社会観や家族制度に関心がある人
1つでも当てはまっていればOKです!
↓↓谷崎潤一郎の小説も読める本屋カフェはこちら↓↓
記事|【阪神間>三田】JR三田駅周辺と、本となごみの空間オクショウ
本記事の内容
谷崎潤一郎の人生
1886(明治19)年~1965(昭和40)年、79年の人生です。東京生まれで関東に住んでいましたが、関東大震災があってから関西に移り住みました。
結婚は3回。それ以外にも妻の妹や姪に熱心になることも多く、周りの女性によく興味を持つ人(笑)です。
どちらかというと古風な顔の3番めの妻、松子さんが今作の春琴のモデルのようです。
関西弁、特に女の人がしゃべる関西弁を好んだことが、出身地ではないのに長く住み続けた要因のようです。
阪神間である芦屋市に谷崎潤一郎記念館が立っているので、細雪やほかの作品を読み進めてから訪問してみたいです。
春琴抄の感想(ネタバレ注意)
優秀な女の子だが9歳で盲目になってしまう主人公
鵙屋(もずや)の娘・春琴は5人兄弟だが2人の兄よりも賢く舞がうまく容貌もきれいでおまけに愛嬌のある性格でした。九歳で盲目になってしまうのは不運な病気か、うらみをかった誰かにやられたかはわからないが、そういうあやふやな怖い事件は明治時代くらいなら本当にありそうな気がします。視力を失ったことから音楽を極めるようになり、やがては師匠になります。師匠になったのは、退屈で八つ当たりするなど性格が悪くなっていく春琴に仕事を与えるという目的もあったが、楽器の腕は確かでした。
明治期の大阪が垣間見える文章
大阪の明治期の話し言葉が書かれていて、それを脳内再生すると世界感にすぐ入り込めます。ただ、昭和一桁生まれの祖母の大阪弁を聞いていた経験があるのでだいたいわかるものの、他地方の人、いや大阪人でも読みにくいかもしれません。それは、巻末に注解(注釈)が大量についていますが、”「出な」:出ないと、の意”が説明されているところから想像できました。関西人なら普通に使っているけど、他地方の人には訳のわからない日本語というのが結構多いのかもしれません。
当時の妊娠や養子にふつうに出す感覚、今の色々なタブーはいつから?
春琴が妊娠したが相手がだれか口を割らぬまま出産し、子は間もなく養子にもらわれていったので、結局その一件はなかったように暮らしは続いた、というエピソードが、現代より合理的な気がしました。
子供の身になれば実親と離れてかわいそうだと現代の感覚では思いますが、養子にもらうということが頻繁にあって、父母+子の核家族ではなく祖父母、おじおば等のいる大家族だったら、養子自身もそんなに自分が特別だとか感じなかったかもしれないなと思いました。
今の時代でも、養子になって安定した気持ちで生活しているかたも多くいらっしゃると思うし、みんながそうであることを願うが、世間からの余計な情の掛けられ方はまだあるかもしれない。”まだある”というと昔からあるようにきこえるが、明治まで遡ると私が想像するにそうでもなさそうです。
だとしたら今、養子に余計な情をかけているのは誰なんだろう?”実父母+子”の一様な家庭環境づくりを目指そうとがんばってくれた昭和の大人たちが今の日本人の考えをつかさどっているのか?ギリ昭和生まれの私からすると上の世代が築いてくれた事柄の中で由来が分からないこともたくさんあり、それに行動・常識を決められていることがとても多いと感じます。
今では使ってはいけない言葉「めくら」や、当事者たちがその反対として「めあき」と言う表現が出てきます。こういう差別用語といわれる言葉は、元々は悪い意味ばかりではなかったと思うが、それを片っ端から全部言い換えていくことでますます前世代の日本語から離れていき、過去の作品が若い世代には読みづらくなってしまう気がします。この作品ではないですが、例えば、ちほう症→認知症、黒人→アフリカ系アメリカ人?のような変換もあります。
異常ともいえるほどに寄り添う少年、佐助
九歳で方向転換を余儀なくされ、卑屈になっていく春琴にも助け船はあり、それは鵙屋の家業薬商の丁稚奉公に来ていた佐助という4歳上の少年の存在でした。春琴の手曳きという役になり、三味線の師匠の家などに手をひいて連れて行くのですが、それだけではなく、食事、トイレ、風呂なども手伝う立場になります。春琴は佐助にもずっと意地悪く高慢な態度ですが、困ったことか幸いか、佐助は春琴の美貌と楽器の腕に陶酔しておりすべて受け入れています。
佐助は中年期に春琴の顔が傷つけられた一件から、顔を見ては失礼だからと自分も盲目の世界に入ってしまいます。同じ盲目の立場になったことでようやく壁がなくなったような二人。”めあき”では分からない第六感が冴えて今までより幸福になったと感じたそうです。
ウグイス飼うのが明治セレブの趣味
春琴はお嬢様育ちで浪費家で、中でもウグイスを飼うのはお金と時間と人手のかかる趣味でした。完璧な餌の作り方や、小屋の仕立てに、その個体の生来の素質を持って、完璧な鳴き声に育て上げます。現在だとオーディオ・音響趣味のようなものでしょうか。
「ホーキーベカコン」と鳴けるのが最上級のウグイスらしいのですが、それってどういう声よ?、、答えは出ませんでしたが、”ホーキーベカコン”という春琴抄を元にした漫画があることを知りました。インパクトのある単語には間違いありません。
春琴抄の映画化 山口百恵・斎藤工
春琴抄は映画化されていて、山口百恵・三浦友和夫妻(1976年)と、斎藤工ら(2008年)が演じたものなどがあります。
![]()
![]()
いろいろと印象的な部分があり、なかなか忘れることはできなさそうな小説でした。
まとめ
- 谷崎潤一郎の人生:
- 1886年に生まれ、1965年の79歳まで生きた。関東大震災後に関西に移り住み、3度結婚するなど女性に興味を持ち続けた。
- その中でも古風な顔立ちの3番目の妻、松子さんが「春琴抄」のモデルとされる。
- 関西弁を好み、阪神間の芦屋市に谷崎潤一郎記念館がある。
- 春琴抄の要約:
- 主人公の春琴は優秀な女の子だが9歳で盲目になる。音楽を極め、三味線の師匠となる。
- 明治期の大阪の雰囲気が文章に表現され、巻末の注解が地域特有の言葉の理解に役立つ。
- 当時の社会観が描かれ、妊娠や養子に関する事柄が合理的であると感じられる。
- 春琴と佐助の関係:
- 盲目となった春琴に寄り添う少年、佐助の存在が描かれる。春琴に助けられながら彼女の世界に入り込む。
- 春琴が顔を傷つけられた後、佐助も盲目になり、二人の間に壁がなくなる。
- 春琴の趣味:
- 春琴はウグイスを飼うことを好み、完璧な鳴き声を楽しむ。この趣味は当時のセレブの娯楽として描かれる。
- 最上級のウグイスの鳴き声は「ホーキーベカコン」。これをタイトルとした漫画もある。
よろしければ読んでみてください!
最後までお読みいただきありがとうございました。